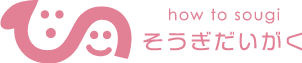仏壇は、人生の中で買う機会が少ないものの一つです。
そのため、購入した後の供養など、宗教的な作法について知らない方も多いでしょう。
この記事では仏壇を購入した後などに行う「開眼供養(魂入れ)」について、詳しく解説していきます。
仏壇の「開眼供養(魂入れ)とは」「どのタイミングでするのか」「しないとどうなるのか」「開眼供養(魂入れ)の作法や費用」といった内容を説明して致します。
あまり知識がないという方も多いと思いますので、ぜひ最後まで読んで参考にしていただければと思います。
目次
仏壇の開眼供養(魂入れ)とは

「開眼供養(魂入れ)」という言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃると思います。
ここでは、「開眼供養(魂入れ)とはどういったものか」「その由来」「開眼供養(魂入れ)をしないといけないのか」といった事柄についてみていきます。
仏壇の開眼供養(魂入れ)とは
仏壇やお墓を新たに購入した場合などに行われる法要です。
この法要を行うことによって、位牌やお墓に故人の魂が宿り、礼拝の対象となるのです。
仏壇の開眼供養(魂入れ)の由来
日本に仏教が伝わったころから、仏像を建立した際には、最後の工程として「眼を描き込む」を残していました。
仏像に目を描き込むことによって、人の手で作られた物体が、仏の尊い魂が宿り信仰の対象として完成することになるとされていたのです。
ここから開眼供養(魂入れ)の法要が広まっていったとされています。
仏壇の開眼供養(魂入れ)しないといけないのか
開眼供養(魂入れ)の法要は、必ずしないといけないのでしょうか。
実は、仏教の中でも、浄土真宗においては本尊に魂を込めるという概念がなく、阿弥陀如来だけを仏様として信仰しているため、開眼供養(魂入れ)といったことはしません。
そのかわり、「御移徙」(ごいし、おわたまし)と呼ばれる慶事の法要を営むことになっています。
真言宗の仏壇の開眼供養については、こちらに詳しく記してあります。 続きを見る

仏壇の開眼供養【真言宗】の4つのポイント 解説
仏壇の開眼供養(魂入れ)をするタイミング

仏壇の開眼供養(魂入れ)をするのは、どういったタイミングになるのでしょうか。
ひとつずつチェックしていきましょう。
新しい仏壇を購入した時
新しい仏壇を購入したときには開眼供養(魂入れ)を行います。
お店で購入した場合は、お店の方から開眼供養についての説明があると思います。
インターネットで購入する方もいらっしゃいますが、そういった場合でも忘れずにしておきましょう。
古くなった仏壇を買換えた場合は、開眼供養の前に古い仏壇の「閉眼供養(魂抜き)」を先に行います。
不要になって閉眼供養した仏壇は、そのまま粗大ゴミとして廃棄しても問題ないですが、気持ちのうえで気が引けるという人も多いでしょう。
仏壇店によっては下取りや無料で引き取りをしてくれるところもあるので、購入したお店で相談してみるといいでしょう。
![]()
引越した時
引越で仏壇を新居に移す場合にも、同様に、引越前の「閉眼供養(魂抜き)」と引越先での「開眼供養(魂入れ)」が必要になります。
仏壇店で仏壇の引越作業をしてくれるところがあるので、多少費用は掛かりますが、そちらに相談してみるといいでしょう。
仏壇の配置やお供え物については、こちらで詳しく紹介していますのでご参照ください。 続きを見る

【仏壇】の配置、お供え物の仕方など紹介します!
仏壇を同じ家屋内で移動した場合は、開眼供養(魂入れ)はしない
同じ家屋の中で違う部屋に仏壇を移動するような場合には、「開眼供養(魂入れ)」の法要は不要です。
家の外に運び出す場合にのみ必要になりますので、ご注意ください。
仏壇の設置する際の方位や向きについては、こちらの記事を参考にしてみてください。
本位牌を供えるとき
葬儀の際に用意した位牌は白木で、仮のものになります。
漆塗りの本位牌ができたところで、白木の位牌から本位牌に先祖の魂を移すということで開眼供養(魂入れ)の法要を行います。
通常は四十九日の法要と併せて行うことが多いようです。
仏壇の開眼供養(魂入れ)しないとどうなるのか

開眼供養(魂入れ)というのは、宗教的な意味合いで行う儀式です。
もし、新しい仏壇を購入しても開眼供養(魂入れ)をしない場合に、何か不都合なことが起こるわけではありません。
しかし、お店にあった仏壇を購入して自宅に移動し、開眼供養(魂入れ)を何もしなければ、単なるものであって、毎日その仏壇に手を合わせる対象とはならないと思う人も多いでしょう。
日々の暮らしの中で拝む仏壇に、先祖の魂が宿っていると思えるほうが、心の安らぎにつながるのではないでしょうか。
仏壇の開眼供養(魂入れ)はどこに依頼するのか

新たに仏壇を購入したり、引越で仏壇を移動することが決まったりした場合には、どこに開眼供養(魂入れ)をお願いすればいいのでしょうか。
ここでは、開眼供養(魂入れ)をどこに依頼するのか、法要はどこで行うことになるのか、について説明していきます。
依頼先
開眼供養(魂入れ)の法要を行うことが決まったら、まずは菩提寺に相談してみることです。
宗派や地域によって開眼供養(魂入れ)の作法が異なりますし、そもそも浄土真宗では開眼供養(魂入れ)の法要をしません。
事前にしっかりと確認をしておきましょう。
仏壇店においても開眼供養(魂入れ)の相談を受け付けているところが多いので、菩提寺と付き合いがあまりなければ、お店の担当者に詳しく相談してみるといいかもしれません。
場所
開眼供養(魂入れ)の法要を行う場所は、仏壇がある場所になります。
位牌をお寺にもっていって供養してもらうことも可能です。
遠方に引っ越す場合などは、菩提寺に相談し、近くにある同じ宗派のお寺を紹介してもらって、そのお寺の僧侶に依頼するといいでしょう。
仏壇の開眼供養(魂入れ)の準備と当日の流れ

実際に開眼供養(魂入れ)の法要をする際に、どのように行うのか、準備するものは何があるのかといったことについて、詳しくみていくことにしましょう。
日程
親族が亡くなって、新しい仏壇や本位牌を用意するのは、多くの場合、四十九日の法要のタイミングに合わせて行います。
新しい仏壇が四十九日法要に間に合わない場合には、一周忌に合わせて開眼供養(魂入れ)をしてもらいます。
用意するもの
お花は、開眼供養(魂入れ)の法要に使うものと花屋さんに伝えれば、それに合ったものを用意してくれます。
お供えするお膳や菓子、果物といったものを用意しておきましょう。
開眼供養のために、赤い和ろうそくを使うというところもあるようですが、地域や宗派によって異なるので、菩提寺に確認しておいたほうがいいでしょう。
服装
開眼供養(魂入れ)の法要には、礼服を着用するというのが一般的です。
新しい仏壇を設置した場合は、慶事となるので通常のスーツでも問題ありません。
四十九日法要と一緒に行う場合は、四十九日法要と同じ喪服を着用します。
当日の流れ
開眼供養(魂入れ)の法要の当日の流れは、次のようになります。
1.開眼供養
仏壇の前で僧侶が読経し、参列者が焼香をします。開眼供養のみの場合は、この後に会食となります。
2.四十九日法要
僧侶は慶事用から弔事用に着替えて、読経を行います。
3.会食
法要後には参列者で会食します。この時に僧侶にお布施を渡し、参列者には引き出物を手渡します。
仏壇の開眼供養(魂入れ)にかかる費用

開眼供養(魂入れ)を行った際にどのぐらいの費用がかかるのか、気になるところです。
おおよその金額をご説明しますので、参考にしていただければと思います。
お布施
開眼供養(魂入れ)のお布施の相場は、3万円~5万円です。
開眼供養と併せて四十九日法要などを一緒に行う場合は、同額が上乗せになります。
お布施の他に、御車代(5000円程度)、御食事代(僧侶が会食に参加しない場合。5000円程度)が必要になります。
食事代
会食の食事代は、一人当たり5000円程度が相場になります。
その他
法要の引き出物として、参列者に3000円程度のものを用意します。
【仏壇の開眼供養(魂入れ)しないとどうなる?】仏壇購入や引越した後の作法を解説のまとめ
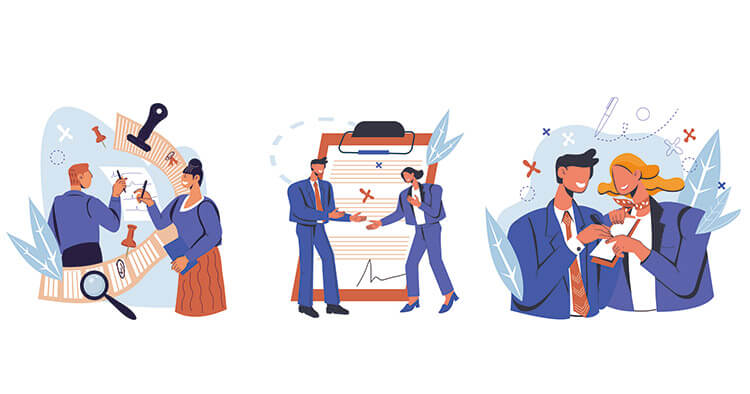
仏壇を新たに購入した場合や、引っ越して仏壇を新居に移動させる際には、仏壇の開眼供養(魂入れ)をする必要があるということをご説明させていただきました。
仏壇の開眼供養(魂入れ)をしないと、仏壇は礼拝の対象とならず、単なるもののまま、ということですので、先祖に対する感謝を示すためにもしっかりと法要することをおすすめします。