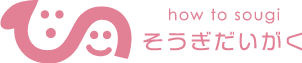全国で、250ほどの互助会が運営されており、会員数は約2240万、前受け金額は2兆5000億円という大きな影響力をもった組織です。
仕組みとして、毎月1000円~5000円程の少額の積立を続け、そのお金を活用することで結婚式や葬儀を執り行う互助会は、一定の評価を受け、長年にわたって会員を増やしてきました。
しかしながら、時代の移り変わりによって、結婚や葬儀に対する考え方も変わり互助会に求められる役割も変わってきています。
この記事では、時代とともに互助会が必要とされてきた背景とその理由、そして今後、互助会が必要とされるための在り方といったことをまとめてみました。ぜひ最後までお読みください。
目次
冠婚葬祭互助会の成り立ち

戦後間もない1948年に生まれた冠婚葬祭互助会は、まだ物資が少ない社会情勢の中で、相互扶助の精神を基盤にして多くの人が出した少額の積立金を集め、そのお金で施設や設備を備えて人々の冠婚葬祭を執り行っていきました。
高度成長時代には、若い人たちが都市部に集まるようになったことで、結婚式場を行うというニーズが高まり、互助会の会員を増やすことになります。
その後、バブル期には豪華な結婚式に多くの人が参加するスタイルが広まり、互助会でもそうしたニーズに対応する施設を立ち上げていきました。
しかしバブル崩壊後は、女性の社会進出もあって、結婚年齢も高まり、地味婚といわれる小規模で自分らしい結婚式を望む人が増えました。また同時に少子高齢化の傾向が進んだこともあって、葬儀に対するニーズが高まり、互助会は次第に結婚式から葬儀にシフトしていくことになりました。
かつては各家庭で執り行われていた葬儀も、都市部を中心として葬儀用のホール・会館に場所を移すようになり、それに伴って互助会でも次々に葬儀用の会館やホールを立ち上げて対応するようになったのです。現在では、多くの冠婚葬祭互助会において、葬儀関連の業務がメインとなっています。
ただし、ここ最近の傾向としては、葬儀にかける予算もだんだん少なくなり、参列者の数も減っていく傾向があります。家族葬を中心として、小ぢんまりとした葬儀が増えてきており互助会へのニーズも変わってきているようです。
互助会の仕組みや成り立ちについては、こちらの記事に詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。
-

【冠婚葬祭互助会とは】互助会はどういう仕組み?成り立ちや特長等を詳しく説明
続きを見る
冠婚葬祭互助会が必要とされる理由

これまで冠婚葬祭互助会が必要とされていたのには大きな理由があります。それは、社会的なニーズです。
高度成長時代、若い人たちは地方の農村から工場がある都市部に移るようになります。このころから団地やアパート等の集合住宅がどんどん建設されるようになりました。
地方では、それぞれの家で行われていた挙式も、こうした住宅事情から結婚式場がメインとなり、費用もかさむようになっていきました。
こうした社会の変化に対応して、互助会は会員を増やし、その預かったお金を活用して、次々に結婚式場を立ち上げていきました。
バブル期には、大勢の客を招いた派手な演出の結婚式が増えていきました。芸能人がこぞって豪華な結婚式を挙げたこともあって、若い人たちや親たちが大金を投入して結婚式を挙げていることが話題になりました。
こうした社会の流れによって互助会を必要と思う人が増えて加入者が広がり、豪華な結婚式のために積み立てすることを進めていきました。
バブル崩壊後は、バブル期の反動で派手な結婚式は次第に敬遠されるようになります。それに加えて女性の社会進出が進み、結婚年齢が上がったことや非正規雇用で結婚できない人も増えたことで、結婚式の件数が減り、規模も小さくなっていきました。
それと同時に少子高齢化社会となり、葬儀件数が今後どんどん増えることが見込めるため互助会もそれまでの結婚式から、葬儀に大きくシフトしていきました。
葬儀には、平均200万円という大きな金額がかかることから、日々備えておいたほうがいいと考える人たちが、互助会の方式を支持し加入していきました。
互助会に加入をお考えであれば、「ごじょスケ」でお住まいに近い互助会の資料を簡単に取り寄せることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
全国の互助会から資料請求
冠婚葬祭互助会を必要としない人たち

冠婚葬祭互助会で少額の積立金を続けて、将来に備えるという方式ですが、人によっては必要とされないケースがあります。
例えば、最近では、結婚式や葬儀にこれまでのような大きなお金をかけることに疑問を持つ人が増えています。そのため小規模な家族葬や、式典を行わない直葬といわれる方式を選ぶ人が年々増えているのです。
また、従来の葬儀の形式にとらわれず、自分らしい形で葬儀を行いたいと考える傾向もあって、そういった人たちには互助会の方式は必要とされていません。
また、互助会に積み立てをすることで、お金の自由度がなくなることを嫌がる人にとっても互助会は必要とされないようです。
互助会に積み立てをすると、会員価格で葬儀を行うことができる、また、いざというときにどの葬儀会社にすればいいのか悩まないでいいというのがメリットとしてありますが、逆に言うと、積立金が葬儀費用に固定化されることになり、その他に使うことができなくなってしまいます。解約には10%~20%という手数料がかかることから、簡単に解約できず、固定化しやすいという背景もあります。
昔は葬儀の情報を集めるのも手間がかかって大変でしたが、インターネットによってすぐにお得なプランを探すことができることから、互助会の仕組みにメリットを感じない人も増えているようです。
冠婚葬祭互助会のメリット・デメリット
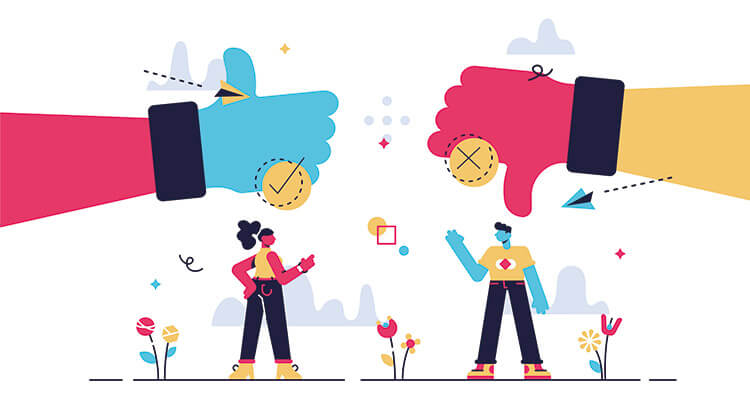
冠婚葬祭互助会に加入することの大きなメリットは、毎月少額を積み立てることで、特段意識せずに葬儀の備えができるということです。
葬儀には200万円近い金額がかかると言われていますが、負担感なく大きな出費に備えることができるのは加入者にとってはとても助かることです。
また、会員特典として、葬儀や結婚式を割引価格で執り行えることや、提携しているお店や会社の商品を特別価格で購入できるということがあります。
こうした金額的なメリットだけでなく、いざというときに葬儀をお願いするところが決まっているという安心感も大きなポイントです。
デメリットとしては、積立金だけでは、葬儀にかかる費用の全額はまかなえないということです。加入者の中には、積立金で全額カバーできると思い込んでいる人も少なくないため、トラブルになることもあります。
葬儀にかかる金額は、式典費用、食事代、宗教者へのお布施を合わせると200万円ぐらいかかるのが相場となっています。互助会の積立金は満期になっても30万円~60万円程度のプランが多いため、不足金が発生し、勘違いしていた人の大きな不満となります。
その他に、退会費用としての手数料がかかることや積み立てたお金は葬儀以外に使えず、利子もつかず固定化してしまうというデメリットがあります。
これから必要とされる互助会の在り方

互助会が誕生して70年以上がたち、社会の在り方は大きく変わりました。インターネットが普及し、誰もが簡単に情報を入手することができる時代になったことで冠婚葬祭に対する考え方も変わっていったのです。
互助会が提案するサービスの内容も、事態の変化に合わせて変えていく必要があります。
多様化するニーズに対応したサービスをこれからも提供していくことが求められています。
多くの会員を抱える互助会ならでは強みを活かした方向を考える時ではないかと思われます。
こちらの記事には、売上を含めたトータルの互助会ランキングとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。
-

【互助会ランキング】冠婚葬祭互助会のランキング上位5社を詳細にご紹介!
続きを見る
また、売上による互助会のランキングについては、こちらの記事をご参照ください。
-

【冠婚葬祭互助会売上ランキング】上位5社の特徴とは?コロナの影響と今後の動向
続きを見る
【冠婚葬祭互助会は必要か?】これまでの互助会の歩みと今後の在り方まとめ

互助会の仕組みと精神が、社会から必要とされていた時代があり大きく会員を増やすことができました。
冠婚葬祭に対する人々の考え方は、社会の変化とともに移り変わっていきます。互助会の在り方も、そうした変化に対応し、必要と思われるサービスを考え提供していかなければなりません。
少子高齢化時代において、葬儀の件数は増えていますが、葬儀にかける費用は徐々に下がってきています。こうした状況でも加入者の満足につながるサービスを提供することが求められています。