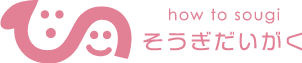全国で執り行われる葬儀の20%弱が互助会によって執り行われており、「互助会」という名前を聞いたことがある方は、多いかと思われます。
しかしながら、互助会について詳しく知っている方は意外に少なく、互助会の運営をしている会社については、ほとんどの方が知らないのではないでしょうか。
この記事では、運営している会社について、どういった会社なのか、経営状況やグループ企業などについても詳しくご紹介していきたいと思います。
これから互助会への加入を考えている方には、運営会社のことも知っておいたほうが安心できることと思います。
また、これまであまり考えたことがなかった方にも、自分や家族のもしもの時のことを考えるきっかけにしていただければ幸いです。ぜひ最後までで読んで参考にしていただければと思います。
互助会に加入をお考えであれば、「ごじょスケ」でお住まいに近い互助会の資料を簡単に取り寄せることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

目次
互助会を運営する会社とはどんな会社か

一般に「互助会」と呼ばれている多くは、「冠婚葬祭互助会」のことを指します。
冠婚葬祭にかかる費用を、毎月少額の積立を続けることで賄っていく会員組織です。
互助会とはどういった組織なのかは、こちらの記事に詳しくご紹介しています。 続きを見る
![]()
【互助会とはどんな組織?】互助会の仕組みや歴史、選び方などを詳しく解説
日本全国には約250の互助会組織があります。
これらを運営しているのが、どういった会社なのか、そこから見ていくことにしましょう。
葬儀会社
冠婚葬祭のうち大きなものは、結婚式と葬儀ですが、近年は少子高齢化の影響によって、互助会の大きな柱は葬儀となっています。
万が一の時に備えて互助会の会員となる方も多くいらっしゃいます。
会員の方の葬儀をトータルでサポートする葬儀会社が互助会を運営するという形は会員と葬儀会社の両者にメリットがあります。
社会全体で高齢者が増えていることから、こうした葬儀会社が運営する互助会では会員獲得に力を入れています。
結婚式企画会社
結婚式は華やかなセレモニーとして費用も掛かることから、互助会に加入し積立をしていくケースも少なくありません。
結婚式は、総合的に支援する企画会社が、会場手配、式の企画から当日の運営までサポートすることが多いです。
互助会として会員向けのプランを打ち出し、自社で保有する施設を使った結婚式を提案している会社も少なくありません。
互助会の仕組みや成り立ちについては、こちらの記事に詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。 続きを見る

【冠婚葬祭互助会とは】互助会はどういう仕組み?成り立ちや特長等を詳しく説明
企業にとって互助会運営のメリット
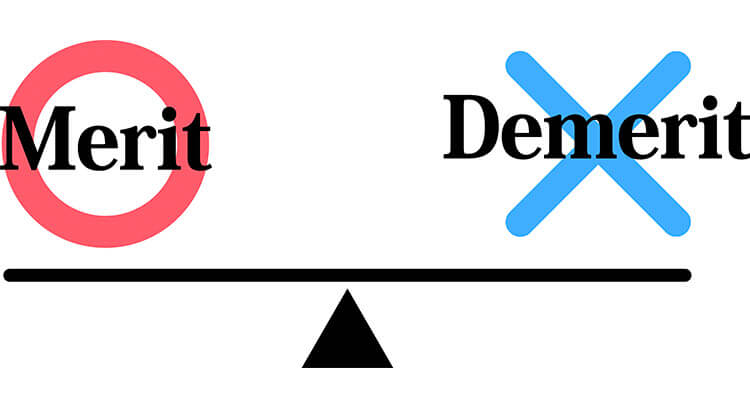
互助会組織は全国に広がっています。
これらを運営する企業にとってどういったメリットがあるのかを具体的にみていきましょう。
会員化で経営安定
互助会の会員となるということは、自社のサービスを利用するお客様になるということに繋がります。
会員を増やすことで、将来の売上を確保できることから、企業にとっては経営を安定させるメリットがあります。
葬儀の場合は、いざというときに時間が限られていて、どこの葬儀会社に依頼すればいいのかわからない、という方が多いため、互助会に加入することで安心する方も多くいらっしゃいます。
会員にとってもメリットがあるといえます。
会員サービスにも力を入れる互助会も多く、会員獲得に力を入れています。
資金活用
互助会組織では、会員が毎月少額の積立を長期に渡って続けていきます。
実際にサービスを提供するまでは時間があるため、その間は積立金を事業に活用していくことができます。
実際、多くの会員を持っている互助会では豊富な資金を活用して、次々に式場施設を立ち上げ、それがまた新たな会員獲得につながっています。
また、グループ会社を設立して、トータルでサービスを提供するようになっています。
互助会を企業が行うには
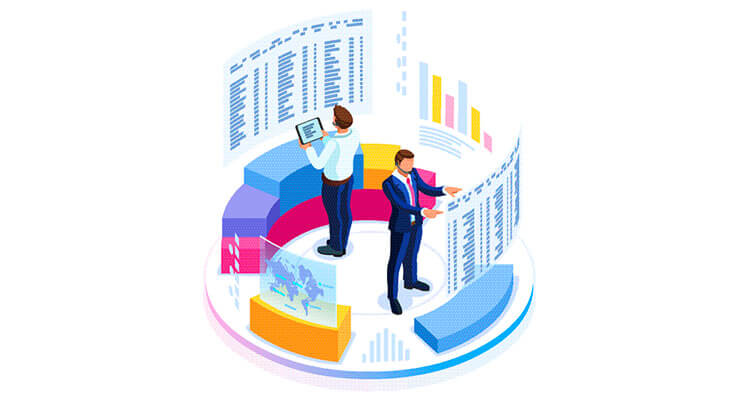
このように互助会の運営は企業にとって大きなメリットがあります。
しかし、どんな会社でも互助会を運営できることになると、問題もありそうです。
ここでは、企業が互助会を運営することができる条件とその理由についてご紹介していきます。
互助会は営業許可のある企業だけが行える事業
互助会には企業にとって、将来の売上と資金確保という大きなメリットがあります。
そこで、自社でも互助会を運営したいと思うかもしれませんが、互助会はどの会社でも行える事業ということではありません。
互助会事業は全て経済産業省の許可を得る必要があり、掛け金の保全措置の仕組みを設定することのほかに、財務内容、事業計画、約款の内容、相談窓口の設置といったきびしい条件を満たす必要があります。
なぜ許可が必要なのか
互助会を立ち上げるのに、こうした条件をクリアしなければならないのには理由があります。
それは、冠婚葬祭互助会の事業形態は、割賦販売法の前払式特定取引業に該当するためです。
月々の分割払いで、お金を預かっておき、必要な時になってサービスを提供するということなので、預かったお金の管理がきちんとできていないと、会員に大きな不利益が生じる可能性があります。
最悪の場合、企業が倒産してしまって、積立していたにもかかわらずサービスを受けることができず、返金もないという可能性もあります。
そのため、互助会では、国が指定する保全機関と保証契約を結び、掛金の1/2相当額を保全しています。
互助会と運営する会社については、こちらにも記事としてまとめています。 続きを見る

【冠婚葬祭互助会の運営会社】どんな会社が運営してる?関連会社と事業の仕組み
互助会企業の業界団体とは

互助会事業は1972年(昭和47年) に経済産業省の許可事業に指定されることになり、会員から預かった積立金をきちんと管理できるよう、明確なルールによって運営されることが求められるようになりました。
互助会事業全体の業界団体を立ち上げ、業界全体で法令順守や会員の満足度向上に努めることとなっています。
現在、互助会運営会社の業界団体として二つの協会があります。
それぞれどのような活動を行い、互助会の運営会社をまとめているのか、見ていくことにしましょう。
一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会
日本全国の互助会の前受金残高ベースで98%、208社が加盟するのが、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会です。
独自の全国ネットワークを構築しているため、加入者が転居した場合でも転居先の互助会にこれまでの積立金を引き継げるようサポートしています。
また、加入者の利益を保護するため、1千億円の基金を設けて、万が一、加入している互助会が破綻しても結婚式や葬儀が間違いなくできるような仕組みを構築しています。
一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助支援協会
全国の冠婚葬祭互助会のうち、55社が参加する業界団体が、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助支援協会です。冠婚葬祭に関する儀式の研究及び教育、市場分析、冠婚葬祭用具等の購買斡旋、冠婚葬祭に関わる教育情報提供事業等を行っています。
互助会運営会社の経営状況
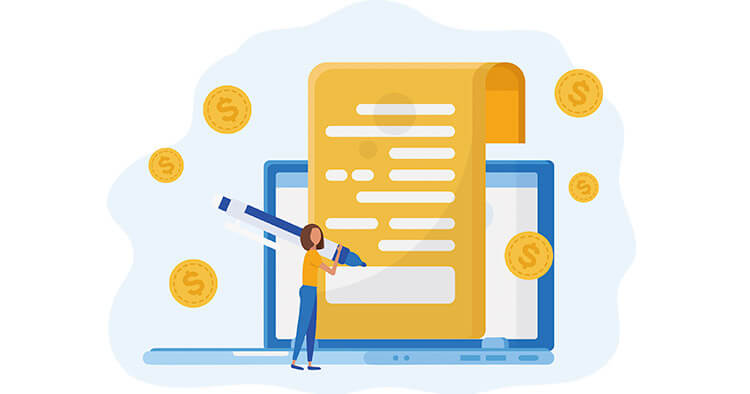
社会の移り変わりとともに、互助会運営会社の経営状況も大きく変動しています。
ここでは、運営状況がどのようになっているのかを見ていくことにしましょう。
互助会の経営動向
互助会組織は、バブル期のピーク時には400を超えていましたが、次第に数は減ってきており、現在は250ほどになっています。
それに対して、互助会全体の前受け金は右肩上がりに増えてきており、1件当たりの単価が上がっていることが分かります。
互助会の事業環境の変化と対応
高度経済成長期には、ベビーブームを先取りする形で、結婚式場を次々に建設していきました。
集合住宅の急増やプライバシーに対する意識が強くなったこと等から、自宅葬から斎場葬へシフトし1990年代後半以降は、斎場が相次いで建ち始め、6000以上のホールが誕生しました。
しかし、過大な設備投資や市場の飽和・競争激化等により、財務状況が悪化する互助会が急増します。
破綻する互助会組織もありました。
バブル期以降は、経済産業省の指導で検査・監督を強化し、平成17年から10年間かけて財務健全化への取組を促進してきました。
近年は、冠婚葬祭に対する価値観が多様化し、様々なニーズに対応することが求められています。
売上の傾向
2020年からの新型コロナウイルスは、冠婚葬祭業界に大きな影響を及ぼしました。
軒並み20%~30%以上の売り上げダウンとなりました。
2021年からはワクチンの普及等により次第に回復基調となっています。
今後は新しい形の冠婚葬祭に対応することが必要になっています。
互助会のグループ企業とは

互助会の運営会社では、互助会組織を中核としてグループ会社を形成しているケースが多くみられます。
こうしたグループ会社をどういった業種で作っているのか、そのメリットはどこにあるのか、といった点についてチェックしていきたいと思います。
グループ企業の業種
互助会では、式場の貸し出し、運営といったところは自前で行っていますが、そこに関わる様々なサービスもグループ会社で提供することがあります。
葬儀においては、お花や飲食、引き出物、貸衣装、車両サービスなどの業種がグループ会社にあります。結婚式では、その他に写真撮影や旅行斡旋といったサービスも加わります。
ホテルを建設し、結婚式場に活用するほか、宿泊施設として運営しているケールもよく見られます。
グループ企業のメリット
結婚式や葬儀の周辺サービスは、それぞれ専門としている業者があります。
もちろん、そちらに依頼するほうが手軽ではあります。
しかし、設備や人材を揃えるコストはかかりますが、自社のグループ企業を立ち上げればグループ全体でさらに売上を伸ばすことができます。
最大手の互助会では、年間数万人の葬儀を執り行います。それらの周辺サービスも自社のグループ企業で賄うことができれば大きな売り上げになるのです。
また、グループ企業であれば、互助会の会員向けに特別なサービスを提供するなどの融通をきかすことができ、運営もしやすいというメリットがあります。
互助会運営する上位ランキングの会社

ここでは互助会を運営する会社の中から上位にランキングされている5社を紹介していきたいと思います。それぞれが多くの会員を抱え幅広く事業展開しています。
株式会社ベルコ
昭和44年(1969年)に兵庫県西宮市で創業。現在は北海道・秋田・岩手・宮城・茨城・福島・富山・愛知・大阪・兵庫・奈良・和歌山・三重・山口・香川・高知・島根・福岡と全国各地で事業展開しています。
加入口数は263万口で、年間4万人を超える人がベルコで葬儀を行っています。結婚式場30ヵ所以上、葬儀などを行う多目的ホール200ヵ所以上を保有する他、ホテルやコスチュームサロンなどの関連施設を有しています。
ベルコが運営する互助会についてはこちらの記事もご参照ください。
株式会社メモワール
昭和45年(1970年)に神奈川県で創業したメモワールは、神奈川・東京・静岡・山梨で互助会の事業を行っています。
約33万人の会員を抱え、2か所の結婚式場と30か所の葬祭施設を保有しています。
メモリードグループ
メモリードグループは、昭和44年(1969年)に長崎県で創立されました。
長崎・佐賀・福岡・宮崎・群馬・埼玉・東京の各エリアを4つの会社で運営しています。
全国に約190ヵ所の施設を保有しており、年間に約4000件の結婚式と、18000件近くの葬儀を執り行っています。
株式会社互助センター友の会
昭和48年(1973年)に東京都豊島区で創業し、東京、埼玉、茨城、山梨、長野が事業エリアとなっています。
会員数約57万口。結婚式場を4か所保有し、友の会グループの「あんしん祭典」は55ヵ所に展開しています。
株式会社京阪互助センター
昭和46年(1971年)に大阪で創業しました。
大阪と和歌山を営業エリアとして稼働しており32ヵ所の葬儀施設と2か所の冠婚施設を保有しています。
【互助会を運営する会社とは?】経営企業の状況やグループ会社をくわしくチェック!のまとめ

これまで互助会について、あまり馴染みがなかったという人も多いと思いますが、この記事をお読みいただいて、大まかにはご理解いただけたのではないでしょうか。
互助会は社会の変動によって浮き沈みがありましたが、社会のニーズに合わせてサービスを提供することで、これからも一定の存在感を示していくことと思われます。
もし将来の冠婚葬祭に備えておきたいと思われる方がいらっしゃれば、互助会をひとつの選択肢として検討してみることをおすすめします。